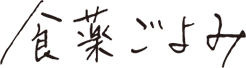12/14
味噌(みそ)・発酵食品
ウイルスが飛び交うこの季節、体調を崩さないように外からも内からもケアすることが大切です。食として強い味方は菌や発酵食ですが、中でも身近なお味噌には様々な高い効能があります。「みそは医者いらず」と昔から言いますが、コレストロールを抑える、美肌効果、がんや糖尿病の予防など良いことづくめ。
簡単なみそ漬け卵黄のご紹介。ちょっと雲丹みたいな味になって、ご飯にもお酒にも最適です。小さめのタッパーなどにみそを3㎝深さ位にひろげ、水でぬらして絞ったキッチンペーパーを上に敷く。卵の殻を押し当ててくぼみを数個作り、そこに卵黄を落とす。みそを薄くぬったキッチンペーパーを上からかぶせ(みその面を下にして)、半日〜4日置き、琥珀色になってきたら出来上がり。この卵黄みそを出汁で溶き、おろしにんにくを加えると、体力回復、風邪などに有効なおみそ汁になります。昔ながらの熟成みしそを日々いろいろな調理法で楽しんで下さい。