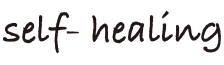2023.5.19
スパイス・ターメリック・スープ

スパイス・生薬・ハーブはナチュラルな薬。栄養価の高い食材と合わせて、スープを商品開発しました。中でも効果の高いターメリックのスープは、独特の苦みや粉っぽさを抜き、生姜やその他のスパイスと合わせて相乗効果のある食べ合わせと調理法で、効能高い美味しいスープに。
黄色の色素のクルクミン(ショウガ科に属する秋ウコンの根茎)は、ポリフェノールの一種。抗酸化作用があり、身体の酸化を抑制するので老化防止に有効、抗炎症作用もあるので、ウイルスなどの感染や炎症を抑制するそうです。アーユルベーダでは、風邪の初期症状には温かいターメリックミルクやラテを飲んだり、傷口ができれば蜂蜜とターメリックを練ったものを塗ることも。ダメージを受けた体内外に有意義な作用を促すターメリックです。
日本では、アルコール分解効果が認知され肝機能を向上させる事が多く知られていますが、その他にもアルツハイマーや認知症予防、鬱症状など脳の悪症状改善に良しとされています。ターメリックは油脂性なので油で炒めるようにし、黒胡椒と合わせると吸収力を大きく上げるようなので、日常の食卓のスープやカレーにご活用ください。