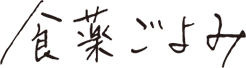10/10
ニュージーランド・アボカド・美肌・ツヤ髪

老化をふせぎ、若返りのビタミンと呼ばれるビタミンEが豊富なアボカド。高い抗酸化作用もあり、女性には特に嬉しいスーパーフードです。アボガトは脂質も栄養価もとても高い果物に分類されます。アボカドの資質の大半は、リノール酸やオレイン酸などの不飽和脂肪酸で、動脈硬化を予防し悪玉コレストロールを減少させます。繊維も多く、1個でさまざまな栄養が摂取できますよ(ただしエネルギーが高いので、食べ過ぎには注意)。中医学では胃腸の働きを良くし、年齢と共に体力の衰えを感じる方にもよいとされています。
温かいアボガト料理も結構いけますよ、半分に割って種をとり、トースターで焼いて醤油とわさびを添えてどうぞ。その他、ねっとりとした舌触りで濃厚な味わいのアボカドにはイムをたっぷり絞り、粗塩で食すのが一番だとアボガト農家さんに伺ったことがあります。
中でもニュージーランド産のアボガトは、あっさりしているようで上質なクリーミーさを合わせ持ちます。アボカド好きも納得するハイクオリティー!何よりビタミンEが豊富なアボカト。高い抗酸化作用があり