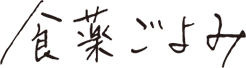11/9
柿・美容薬膳

柿が美味しい季節ですね。ビタミンカラーのオレンジ色が目に飛び込んでくるとついつい手が伸びます。よく熟れた柿を見つけたらつぶしてフレッシュピュレにし、フルンとした杏仁豆腐にトッピングすると、見た目も麗しいデザートに。ビタミンCやカロテンが豊富な柿には風邪予防や美肌に効く効能がたっぷりです。咳や痰の痛みなどを抑える杏仁にも美肌効果があるので、合わせて相乗効果を上げます。
柿のキャロットラペもオススめです、みかんの果汁と塩、オリーブオイルで小粋に。酢の物や白和えにも良いですが、シンプルにレモン果汁をたっぷり絞って冷やしたものも美味。生ハムを添えると塩気と相まって白ワインにピッタリです、柿には、アルコールの解毒作用もあるのでお酒のお供にも最適ですが、カラダを冷やす傾向にあるので、温まるものといただいて下さい。ヘタや葉は生薬です、殺菌効果もあるので、渋柿の若い葉は柿の葉寿司などに活用さますね。
乾燥させたお茶も販売されています、ダイエットにも最適だとか。