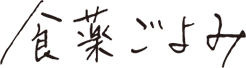12/16
シナモン・スパイス・冷え

シナモンスティックやシナモンパウダーを適宜お茶に入れるのが日課です。
シナモンはスリランカ、インド南部が原産地。日本でも国産のシナモンが温かい地方で栽培され、春に収穫されます。薬膳の肉桂(桂枝)は根っこ部分、樹木のシナモンとは種類が違うのですが、薬効は似ています。冷えをとり五臓を活性化させるとされており、関節痛などの痛みや、血のめぐりの改善に欠かせない生薬です。
体を温める作用は生姜以上とされ、指先などの毛細血管まで温めるそう。体温が上ると免疫力も高まります。身体はなるだけ冷やさないように日頃から気をつけます(首、手首、足首、腰などは特に)。
香りが良いので、リラックスしたい時のお茶にもピッタリです、シナモンをポキっと折った半本と丁子(クローブ)2個、紅茶などの発酵茶適宜を合わせてブレンドティーに。
シナモンはアップルパイなどのお菓子に欠かせませんが、カレーや、醤油味の煮込みにも意外とお勧めです。
私はワインビネガーやお酢にスティックごと漬けてシナモンビネガーとして素敵な香りと効能を楽しんでいます。ドレッシングに加えたリ、マリネに使うとひと味違います。