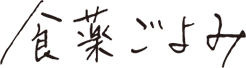4/27
新じゃが芋・ポテトフライ・ポテトパンケーキ

じゃが芋は、ビタミンCが豊富。澱粉に守られているのでビタミンCの損失が少なく調理に向いています。
ポテトサラダなどで余った茹でじゃが芋を少し取り置いて、簡単おやつを作ります。
ホットケーキミックスに茹でたじゃが芋とチーズを混ぜて焼くとポテトパンケーキの完成。柔らかく練ったバターをたっぷり添えていただきます、チーズドッグのような味わいですよ、シロップはお好みで。
柔らかい新じゃが芋は、皮付きフライドポテトにも向いています。下ゆでもいらず、60度位の低温ででゆっくり揚げると酵素で甘みが出ます。粗塩にスパイスを混ぜて、揚げたてにしっかり振ると美味しいですね、パプリカ、挽き立ての胡椒、ナツメグなどミックスすると奥深い風味が生まれます。
学生の頃、友達達とよく食べたシェーキーズの皮付き円形ポテトフライ。ソルトペッパーたっぷりが、未だに私の中のポテトフライモデルです。じゃが芋の栄養成分は皮に近い部分なので、ぜひ皮ごといただいて下さい。