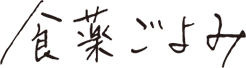8/5
葉生姜・新生姜・生姜つくねの作り方

『葉しょうが』は柔らかく筋が無いのにシャキシャキとした食感が魅力的です。旬は6月から8月頃まで。みずみずしく清涼感のある爽やかな香りが際立って、辛味が何とも心地良い野菜です。含まれる辛味成分は食欲増進効果があり、生魚肉の解毒作用、胃もたれ時などにも。
旬の葉生姜は柔らかいので、そのまま味噌やマヨネーズで食したり、美しい色合いを生かした甘酢漬けなどにし、保存すると重宝します。
お勧めの鶏つくねは、消化を促進する生姜成分が肉の油っこさや臭みを断ち切り、肉の脂で辛味がやわらいで食べやすい。焼き鳥屋さんに期間限定であったらつい頼んでしまうような大人つくねです。料理番組でも作ったことのあるメニュー、この時期にぴったりなのでレシピをご紹介します
●葉生姜つくね
材料(約10本分)
鶏ひき肉 200〜250g
卵 1個
おろし玉葱 大さじ2
塩、胡椒 各少々
タレ(醤油・酒・水各大さじ1・みりん大さじ2)
ごま油 小さじ2
作り方
1、葉生姜の葉をフライパンに入る長さに切り、3本を手で折って離しておく。
2、ボウルにひき肉と塩を入れてよく混ぜる。水気をきったおろし玉ねぎ大さじ2、卵白1個分を入れてよく混ぜる。1の葉生姜の先端4、5cmにひき肉をそれぞれ巻きつける。
3、フライパンにごま油をしき、全体に焦げ目をつけるように焼く。フタをして火が通るまで2分ほど蒸し煮にし、Aを鍋肌から加えてからめる。
器に盛って残った卵黄を添える