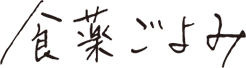10/15
じゃが芋・ジャガイモ・ポテト・肉じゃが

肌寒さを感じるようになると、ほっこりした甘辛い肉じゃがが脳裏をよぎります。じゃが芋4個は4、5等分に切って水に5分放してザルに上げる。玉ねぎ1個は1㎝幅のくし切り、生姜半かけは細切り、鍋を中火にかけごま油大さじ1で生姜と牛細肉250gを炒めて取り出す。同じ鍋で切った野菜をよく炒め、水1カップ、きび砂糖大さじ2、醤油大さじ1を入れて厚手のキッチンペーパーをかぶせフタをして10分煮る。煮汁が半量になったら醤油大さじ2、肉を戻し入れまぜ、時々鍋を揺すりながら10分煮て出来上がり。
じゃが芋のビタミンCはデンプンに守られているので、熱に強く調理に向いています。カリウムの王様とも飛ばれていますよ、塩分を排出するので気になる方におすすめです。薬膳では、胃腸の調子が悪い時や気力を養いたい時にもよいとされる、頼もしい野菜です。